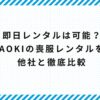長年使ってきたダイニングテーブル。
気づけば、小さな傷・輪染み・筆圧の跡・食器の擦り傷など、表面は傷だらけに…。
「愛着はあるけど、買い替えるのはもったいない」
「でも自分で修理なんてできるのかな?」
そんな思いから、思い切って工具サンダーをレンタルして天板を削り直すDIY修理に挑戦してみました。
プロに頼むと数万円ですが、今回は 合計1,510円(!) で新品のような美しさに。
初心者の私でもできたので、同じ悩みを持つ方の参考になるはずです。
この記事では、
-
ハンズマンでのサンダーレンタルの流れ
-
使ったサンダーと紙やすりの番手
-
失敗しない削り方
-
粉塵対策の超重要ポイント
-
紙やすり節約テク
-
仕上げのワックス塗り
など、実際にやって気づいたことをすべてまとめます。
実際にかかった費用まとめ(総額1,510円)
DIYって費用が読めない…と思う人のために、今回の実費をまとめました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| サンダー(ハンズマン 1泊2日) | 500円 |
| 紙やすり(40円 × 粗・中・細 計3枚) | 120円 |
| アマニ油蜜蝋ワックス | 890円 |
| 合計 | 1,510円 |
まさかの 1,510円でテーブルが新品級に。
DIYのコスパは本当にすごいです。
サンダーはハンズマンでレンタル|実際の流れ
まずは近所のホームセンターへ。ハンズマンでは、サービスカウンターで工具を借りる事が出来ます。
サンダーは購入すると、安いものでも数千円、高性能なものだと数万円クラス。
一方レンタルなら、1日500〜1,000円前後が相場です。
今回私は、1泊2日で約500円でレンタルしました。
年に数回使うかどうか…という工具なら、購入するよりレンタルのほうが圧倒的にコスパがいいと感じました。
-
保管場所を取らない
-
メンテナンス不要(刃の交換・故障対応などを考えなくていい)
-
必要なときだけ、良い工具を使える
というメリットも大きいです。
レンタル時には 身分証明書の提示が必要 でした。
スタッフさんが使い方を一通り説明してくれて、
-
電源の入れ方・切り方
-
紙やすりの付け替え方
-
持ち方・動かし方のコツ
など、基本操作を丁寧に教えてもらえたので、初めてでも安心でした。
紙やすりも何を削るのかを伝えたら、しっかりと教えて頂けました。
今回借りたのはRYOBI製のサンダー。
テーブルのような平面研磨に向いた一般的なタイプで、重さも約1kgと軽く、女性でも扱いやすいモデルでした。
サンダーとは?簡単におさらい
サンダーは、紙やすりを電動で高速振動させて、木材の表面を削るための工具です。
手作業で紙やすりをかけるのに比べて、作業スピードも、仕上がりの均一さも、段違いです。
代表的なサンダーの種類はこんな感じです。
-
オービタルサンダー
…円を描くように振動するタイプ。平面を均一に磨きやすく、初心者向き。 -
ランダムサンダー
…不規則な動きで削るため、削り跡が出にくく、仕上がりがきれい。 -
ベルトサンダー
…ベルト状の紙やすりが高速回転し、ガツンと削れるタイプ。粗削りや大量の削りに向く。
今回使ったオービタルサンダーは、
「テーブルの天板をキレイに平らにしたい」という目的にぴったりの選択でした。
当初、紙やすりで自分で削ればいいかなと思っていたのですが、
とてもじゃないけど、手で削るなんて無理でした💦
レンタルして本当によかったです
紙やすりは3段階で使い分けるのがコツ
サンダー作業の基本は、
粗い番手 → 中くらい → 細かい番手
と、徐々に番手を細かくしていくことです。
いきなり細かい番手で始めると、いつまで経っても古い塗装や深い傷が取れません。
逆に粗い番手のまま終わると、表面がザラザラした仕上がりになってしまいます。
今回は、次の3段階で進めました。
実際の削り手順を詳しくレポート
#60(粗目)|古い塗装と深い傷を落とす「下地づくり」
最初は#60の粗目からスタート。
目的は「古い塗装や深い傷を一気に落とすこと」です。
この番手はかなり削れる力が強いので、
-
サンダーの重さに任せて、上から強く押さえない
-
なるべく同じスピードで、テーブルの端から端まで動かし続ける
-
同じ場所にサンダーを留めない(凹みの原因になる)
このあたりを意識しながら作業しました。
30分ほどかけて全体を削ると、表面の塗装がほとんど落ちて、木の地肌がうっすら見えてくる状態に。
「本当にテーブルを削っているんだ…!」という実感が湧いてきて、ちょっと感動します。


#120(中目)|削り跡と細かい傷をならす
次に#120の中目にチェンジ。
ここでの目的は、#60でついた削り跡や細かな傷をならして、表面を整えることです。
粗目で削った直後の木の表面は、目には見えなくても細かい溝だらけ。
それをなだらかに均していくイメージで、全体を丁寧にサンダーがけしていきます。
この段階になると、削りカス(粉)の色も少し明るくなってきて、
-
古い塗装がほぼ取り切れた
-
新しい木の層が出てきた
というのがわかります。
手で触ると、最初よりも明らかにスベスベしてきて、木目もくっきりしてくるのでやる気がアップします。
#320(細目)|新品みたいな手触りにする「最終仕上げ」
最後は#320の細目で仕上げ。
ここまで来ると、「削る」というより完全に「磨く」感覚です。
-
サンダーを軽く滑らせるように動かす
-
木目に沿って、ムラが出ないように全体を丁寧に
という感じで仕上げていくと、触った時にツルツルの手触りになります。
光に当てると、表面がほんのりと艶やかに光って、本当にきれい。
この時点で、テーブルの印象は「使い込まれた家具」から「新しく生まれ変わった無垢材テーブル」という雰囲気に近づきます。
各番手でだいたい30分ずつ、合計で約1時間半ほどの作業でしたが、
集中しているとあっという間。音楽をかけながら無心で磨く時間は、想像以上に楽しかったです。

紙やすり代を半額以下に節約する裏ワザ
実は今回、紙やすりのコストをかなり抑える工夫をしました。
サンダー専用の紙やすりは、1枚100円ほどします。
3種類の番手で各2〜3枚使うと、それだけで1,000円近くかかってしまいます。
そこで私が採用したのが、大判の紙やすりを買って自分でちぎって使う方法です。
ホームセンターで売っている大きめサイズの紙やすりなら、1枚40円程度。これをサンダーのパッドに合わせて手でちぎって使えば、専用品の半額以下に抑えられます。
この方法のメリット:
- コストが半額以下になる
- 必要なサイズに自由に調整できる
- 余った部分は手作業の仕上げに使える
注意点は、ハサミで切ると刃が傷んでしまうこと。
紙やすりの研磨剤が刃を痛めるので、すべて手でちぎりました。
紙やすりは意外と簡単に手で裂けるので、問題ありません。
この一工夫だけで、紙やすり代が500円以上浮きました。DIYは小さな節約の積み重ねが大事ですね!
粉塵対策は超重要!室内での作業は絶対NG
今回のDIYで、いちばん痛感したのがこれです。
サンダー作業は、絶対に室内でやってはいけない。
最初はリビングでやるつもりだったのですが、
ちょっと削ったら木の粉が空中に舞い、部屋全体がうっすら白くかすむ
そのうえ、粉が細かいので、喉や鼻にも入りやすく、かなり不快です。
健康面を考えても、絶対に室内作業は避けるべきだと痛感しました。
後で掃除機で吸えばいいかなと思っていたのですが、
床だけじゃなくて、かなり空気中を舞うんです!!
サンダー作業で「必ず」やるべき粉塵対策
-
屋外(庭・ガレージ・ベランダなど)で作業する
-
防塵マスクは必須(ふつうの不織布マスクでは不十分)
-
保護メガネで目をガード
-
周囲にビニールシートやブルーシートを敷いて、粉の掃除を楽にする
-
可能なら、集塵機能付きサンダーや掃除機接続タイプを選ぶ
-
風向きを確認し、人や洗濯物がある方向に粉が飛ばないようにする
特に防塵マスクはケチらず、粉塵用のものをホームセンターで買っておくことをおすすめします。
仕上げは「アマニ油蜜蝋ワックス」で安心・安全なテーブルに
サンダーで木地を出したあとは、仕上げとして塗装やオイル・ワックスを塗っていきます。
今回は、ダイニングテーブルということもあり、安全性を最優先に考えて
「アマニ油蜜蝋ワックス」を選びました。
-
自然素材100%
-
万が一口に入っても比較的安心とされている
-
小さなお子さんやペットがいる家庭でも使いやすい
というポイントが決め手です。
塗り方はとてもシンプル
-
柔らかい布にワックスを少量取る
-
木目に沿って、薄く伸ばしながら塗り込んでいく
-
数分おいてから、乾いた布で軽く拭き取る
これだけで、しっとりとした自然なツヤが出て、木の温かみがぐっと引き立ちます。
テーブルを触るたびに、少しうれしくなるような質感になりました。

私の写真撮影技術が下手なので、あまりキレイに見えませんね💦
実際は木のぬくもりがある、とても素敵な仕上がりになったんですよ(^^)
私が使ったワックスはコチラ
アマニ油蜜蝋ワックス → https://amzn.to/48o7RzR
「サンダーを借りたいけど、どこで借りられるの?」という方のために、全国でサンダーをレンタルできる主な店舗をまとめました。DIY初心者の方でも安心して借りられるお店ばかりです。
全国展開している主なホームセンター
カインズ
電動工具のレンタルサービスが充実しており、サンダーも多数取り扱っています。
スタッフの説明も丁寧で、初めての方にもおすすめです。店舗によってはオンライン予約も可能。
https://reserve.cainz.com/lp/tool
コーナン
全国に店舗があり、レンタル工具コーナーが設置されている店舗も多いです。
価格も比較的リーズナブルで、会員になるとさらにお得に借りられる場合があります。
https://www.hc-kohnan.com/service/stores/rental_tool/
DCMグループ(旧ホーマック・カーマ・ダイキ)
統合により全国的にサービスが標準化され、多くの店舗でレンタルサービスを展開しています。地方都市でも利用しやすいのが魅力。
https://www.dcm-hc.co.jp/service/rental_tool/
ハンズマン
九州を中心に展開。地域密着型で、スタッフの対応が親切と評判です。
https://www.handsman.co.jp/diy/service/
レンタルの有無は店舗によって異なります。事前に電話で確認するか、公式サイトでチェックしてから来店すると確実です。「サンダーをレンタルしたいのですが」と伝えれば、在庫状況や料金を教えてもらえます。
ホームセンター以外のレンタルサービス
近くにホームセンターがない、または自宅まで配送してほしい方には、オンラインレンタルサービスも便利です。
オンラインレンタルのメリット・デメリット
メリット:
- 自宅まで配送してくれるので、重い工具を持ち帰る必要がない
- 24時間いつでも予約可能
- 店舗に在庫がなくても借りられる可能性がある
デメリット:
- 送料がかかる場合がある(往復で1,000〜2,000円程度)
- 配送に時間がかかるため、すぐに使いたい時には不向き
- 実物を見てから借りられない
使い分けのコツ:
近くにホームセンターがあって、すぐに使いたい場合は店頭レンタルが便利。配送の手間や時間に余裕があって、自宅で受け取りたい場合はオンラインがおすすめです。
どちらも一長一短なので、ご自身の状況に合わせて選んでくださいね!
やってみて感じたこと|レンタル工具でDIYは十分「現実的」
今回のDIYを通して、強く感じたのはこの2つです。
-
適切な道具さえあれば、素人でも意外ときれいに仕上げられる
-
粉塵対策は想像以上に重要。ここを甘く見ると後悔する
特に粉塵の量は、完全に予想以上でした。
これからサンダーを使う方は、
-
必ず屋外で
-
粉塵用マスク+保護メガネ
-
周囲の養生をしっかりと
この3つだけは本当に徹底してほしいです。
一方で、工具サンダーをレンタルしてみて、「DIYのハードルが一気に下がる」とも感じました。
購入しなくても、数千円の予算で、本格的な家具のリメイクに挑戦できるのは大きな魅力です。
仕上がったダイニングテーブルは、買い替えなくてもまだまだ使えるどころか、
「前より好きになった」と言えるくらい、愛着が増しました。
週末のちょっとしたチャレンジとして、
「ダイニングテーブルのDIY修理+工具サンダーレンタル」、とてもおすすめです!!